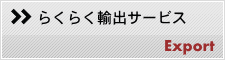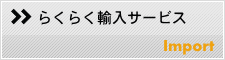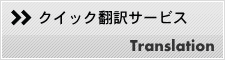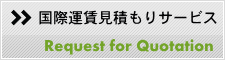トランプ関税が決着
2025-07-25
今回のトランプ関税は、自動車プラスコメ(米)の政府間交渉でしたが、
「お互いに国益を守った」といった論調の報道が多いです。
先人たちのたゆまぬ努力のおかげで、現在の日本経済のグローバル化に思いをいたし、
この機会にいままでの通商交渉を振り返り、「国益とは?」を考えてみたいと思います。
▼ 戦後の日米貿易は、貿易摩擦の連続でした
1960年代の繊維を皮切りに、
70年代前半には鉄鋼製品・カラーテレビ・工作機械・ベアリング、
さらに70年代後半には牛肉・オレンジ、
80年代以降には半導体と自動車が政府間で交渉されてきました。
いままで多国間協議で「例外のない関税撤廃」をめざして交渉が進められましたが、
多くの例外事項が盛り込まれた妥協の産物であったことも事実でした。
そして、今回のトランプ関税のように1対1の関税交渉の時代になりました。
▼ 妥協の産物
多国間の通商交渉は、
WTO(世界貿易機関)になる前のGATT(関税及び貿易に関する一般協定)の時代から
さらに最近のTPPに至るまで、
「例外のない関税撤廃」を目指して関税交渉が続けられてきました。
しかし、関税の変更を行わずに、例外規定を設けるなど妥協の産物が多く行われてきました。
今回、大きな議題に上った778%という高率な「コメ」に別枠で無関税枠を設定した「MA米」は、
まさに「例外のない関税撤廃」にはほど遠い妥協の産物でした。
(それも米国向けの無関税枠数量が最大です)
TPPの時も、そのずっと前のGATT・ウルグアイラウンドの時も、コメが日米間の重要課題でした。
お互いの利害が複雑に錯綜するなかで、日本は、米国に対して、主張すべきことは言い、
問題解決をするために多くの方が尽力されてきました。